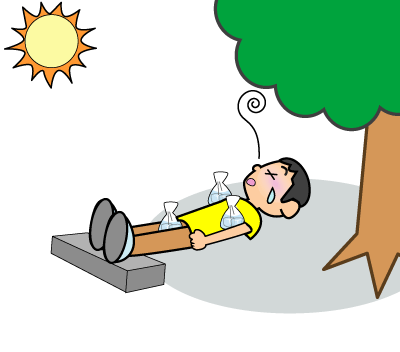小児へお薬を飲ませるコツ
|
子供が病院で薬をもらったんだけど飲んでくれない。どうしたら飲んでくれるのだろう? 小さなお子様へお薬を飲ませるのにご苦労されている親御様も多いのではないのでしょうか? そんなお子様を持つ親御様からよくご質問を受ける「お薬を飲ませるコツ」の一例をまとめてみました。 ご参考になるようなコツがございましたら、ぜひお試しください。 |
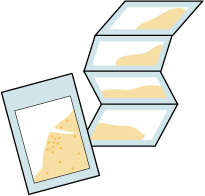
|

|
服薬補助製品
服薬補助製品には、服薬補助器具、オブラート、服薬ゼリーなどがあります。
この中で小さなお子様に使いやすいのが、服薬ゼリーかと思われます。現在市販されている服薬ゼリーにはピーチやいちご、ぶどう、チョコレートなど様々な味が用意され、お子様の好みに合せて飲ませることができるのが利点です。
また服薬ゼリーの利点としては、苦いお薬を口の中で広がるのを最小限に抑えスムーズに飲み込むことができる点です。
方法としてはスプーンに適量の服薬ゼリーを出し、その上に薬剤を置き、さらにその上から服薬ゼリーをかぶせ薬剤を包み込んでしまいます。
市販の服薬ゼリーは、飲み込みやすい柔らかさに調整をされていますが、お子様が服用できるのであれば普通のゼリーでも代用できますし、お子様の好みに親御様でゼリーを作っても良いと思います。
クッキーに挟む
市販されているクリームサンドクッキーを使用します。
お勧めはチョコレート味のクリームサンドで、方法はクリームサンドのクッキーをはがしクリーム面に薬剤をふりかけ、クッキーを戻して
食べさせます。
カカオを使用したチョコレートやココアなどは、特に苦いお薬(クラリス・ジスロマックなど)に有効な場合が多いです。
クッキーサンドだけでなく、飲み物やアイスクリームなどで混ぜて飲ませるときでもチョコレート味、ココア味を選んでみるのも一つの方法だと思います。
海苔のつくだ煮に混ぜる
海苔のつくだ煮に薬剤を混ぜ食べさせる。薬剤を完全に溶かそうとせず、混ぜたらすぐに食べさせるのがポイントです。
練乳に混ぜる
練乳にさっと混ぜ込み、薬剤を完全に溶かそうとせず、すぐに食べさせるのがポイントです。
ジャムに混ぜる
イチゴやリンゴのジャムにさっと混ぜ込み、薬剤を完全に溶かそうとせず、すぐに食べさせるのがポイントです。
シュークリームに挟む
|
子供が一口で食べられるサイズのシュークリームの内部に薬剤を混ぜ込み食べさせる。 |
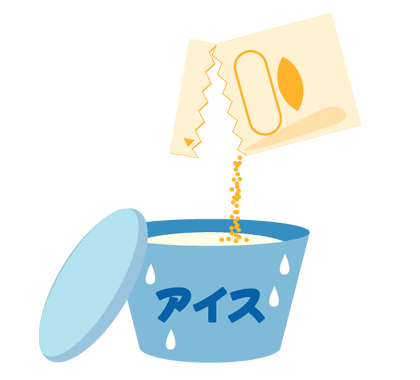
|

|
![]()
苦みが強い薬剤の代表例であるクラリス、ジスロマックなどは苦みが出てこないようにコーティングを施しています。
完全に溶かそうとせずすぐに食べさせたり、飲ませたりするのは、散剤を溶かすことでこのコーティングが剥がれ苦みが出てくるのを回避するのが目的です。
コーティングの有無については、薬剤により異なるため基本の飲ませ方として混ぜたら時間を置かず、すぐに服用ことをおすすめすます。
またジャムや練乳と同様に蜂蜜を使用する方もいらっしゃいますが、1歳未満の乳児には、乳児ボツリヌス症の危険もあるためあまりおすすめできません。
各散剤についての特徴をまとめた「散剤の飲ませ方と特徴(1)」「散剤の飲ませ方と特徴(2)」「散剤の飲ませ方と特徴(3)」もご参考までにご覧くださいませ。
排泄物の色を変化させる薬剤
|
薬によって尿や糞便に色調変化をきたすものがあります。 |

|
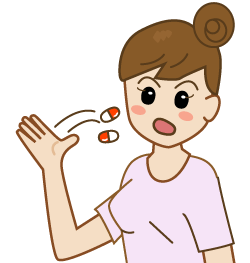
|
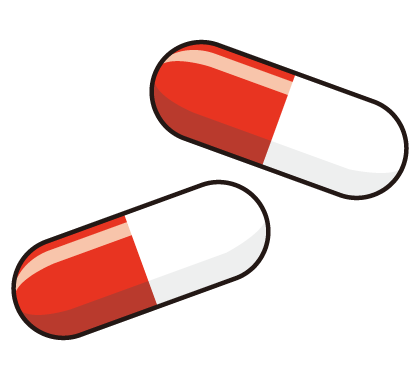
|
排泄物(尿・糞便)の色調変化一覧表
| 成分 | 主な製品名 | 尿の着色 | 便の着色 | その他の着色 |
| FDA、FDAエキス | フラビタン | 黄色 | ||
| エグアレンNa | アズロキサ | 青色 | ||
| エパレルスタット | キネダック、キネックス | 黄褐色~赤色 | ||
| カルバゾクロムスルホン酸Na | アドナ | 茶色~黄褐色 | ||
| クロファジミン | ランプレン | 赤色~茶褐色 | 赤色~茶褐色 | 赤色~茶褐色(汗・たん・毛髪・皮膚) |
| サラゾスルファピリジン | サラゾピリン | 黄赤色(アルカリ尿) | ソフトコンタクトレンズが着色 | |
| セフジニル | セフゾン | 赤色 | 鉄添加製品と併用し赤色 | |
| センナ・センノシド | プルセニド | 黄褐色~赤色 | 黄褐色 | |
| ビタミンB複合剤 | ビタノイリン | 黄色 | ||
| ヒベンズ酸チペピジン | アスベリン | 赤色 | ||
| フルタミド | オダイン | 琥珀色又は黄緑色 | ||
| プロトポルフィリン | プロルモン | 黒色 | ||
| 塩酸ミトキサントロン | ノバントロン | 青色~緑色 | ||
| 塩酸ミノサイクリン | ミノマイシン | 黄褐~茶褐色、緑 | ||
| メチルドパ | アルドメット | 黒(放置で暗色化) | ||
| メトロニダゾール | フラジール | 暗赤色 | ||
| リファンピシン | リファジン | 橙赤色 | 橙赤色 | 橙赤色(唾液・たん・汗・涙液・血清) |
| リボフラビン | ハイボン | 黄色 | ||
| レボドパ製剤 | マドパー | 黒色 | 黒色 | 黒色(汗・唾液) |
| 塩酸セフォゾプラン | ファーストシン | 赤色~濃青色 | ||
| 臭化チメピジウム | セスデン | 赤色 | ||
| 鉄剤 | フェロミア | 黒色 | ||
| 銅クロロフィリン合剤 | メサフィリン | 緑色 |
Read More
熱中症
|
お薬の服用時間
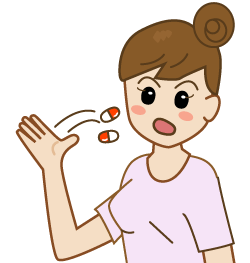
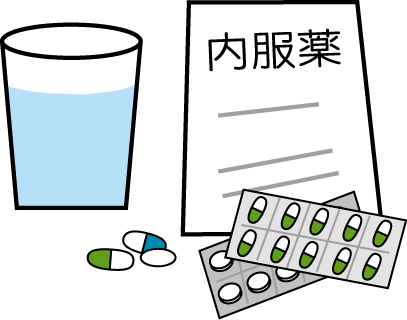
お薬の基本的な飲み方
| お薬はできるだけコップ一杯のお水または白湯で服用しましょう。 最近のお薬は、たいていお茶も大丈夫です。普段お食事のときにお茶を飲まれる方は、そのままお茶で服用しても差し支えは無いと思います。 ただし牛乳やグレープフルーツなどは、ある種のお薬と反応してしまいお薬の効果を妨げたり効きすぎたりしてしまうので注意が必要です。
一番良くないのは、水分なしでお薬を服用することです。水分なしでお薬を服用してしまうとお薬が食道部分で留まり、その部分が潰瘍になる恐れがあるからです。 また決められた服用時間にもそれぞれ意味があり、お薬が最も効率よく安全に効くように試験をされ決められているため医師から処方されたお薬は決められた時間通りに服用してください。
|
お薬の服用時間
1)食後
最も指示の多い服用時間で食後20~30分以内を目安に服用します。食べ物と一緒の方が程良く吸収され胃にも刺激が少ないため多くのお薬が食後に処方されます。また食事の後は一般的に飲み忘れが少ないと言われています。
2)食直後
食事の直後(10分以内)を目安に服用します。食事が終わりお箸をおいてすぐ服用して下さい。
胃を荒らしやすいお薬や脂溶性で食直後の方が吸収の良い吸収の良いお薬が処方されます。
3)食前
食事の20~30分前を目安に服用します。食事の影響を受けやすいお薬、胃の調子を整える食欲増進剤や吐き気を抑えるお薬、血糖値を抑えるお薬などが処方されます。
4)食直前
食事の直前(10分以内)を目安に服用します。食事の際、お箸を持つ直前に服用して下さい。食事の影響を受けやすいお薬や食事による急激な糖の吸収を抑えるお薬などが処方されます。
5)食間
食事と食事の間、およそ食後2時間後を目安に服用します。食事の影響で吸収が悪くなるお薬や胃粘膜を修復するお薬などが処方されます。
6)就寝前
眠る30分前を目安に服用します。不眠の時に使用するお薬や翌朝、排便できるようにするお薬などが処方されます。
Read More
ジェネリック医薬品Q&A
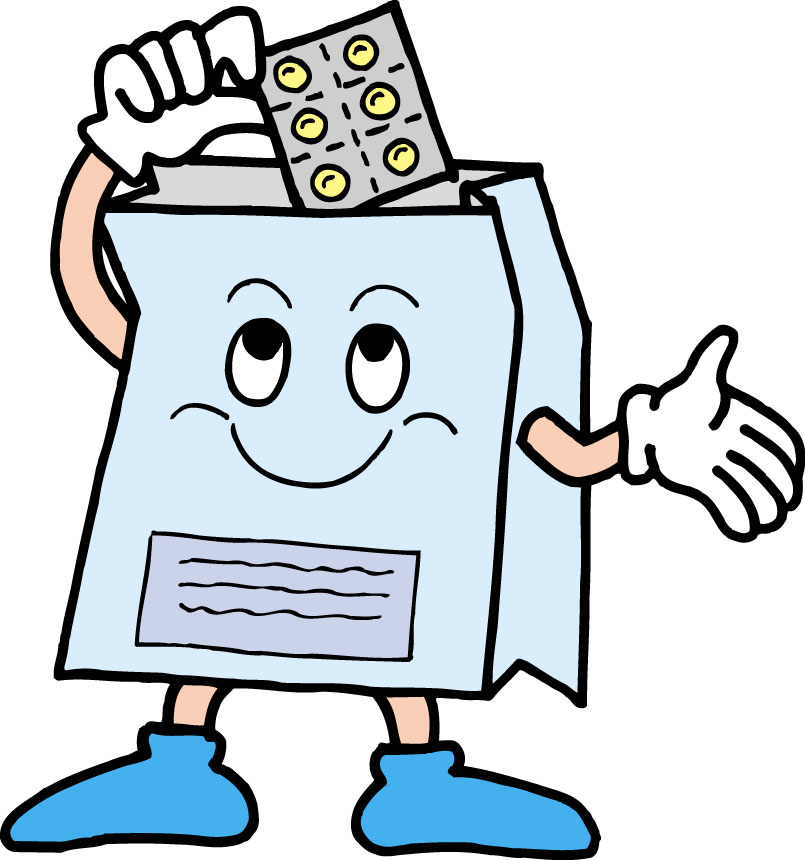
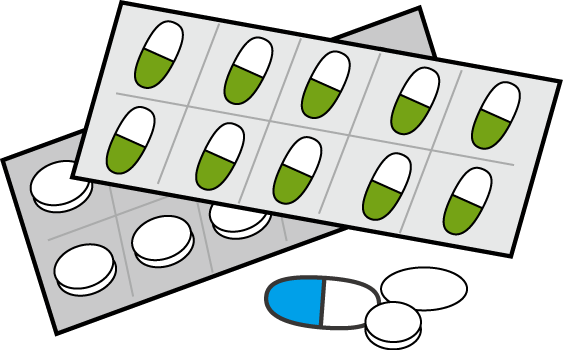
![]()
![]() ジェネリック医薬品ってなに?
ジェネリック医薬品ってなに?
![]() 先発医薬品と同様の有効成分・効果を持つお薬です。
先発医薬品と同様の有効成分・効果を持つお薬です。
ジェネリック医薬品は、新薬(先発医薬品)と同じ有効成分で先発医薬品の特許が切れた後に、厚生労働大臣の承認のもと他社から製造販売されるため、後発医薬品(ゾロ)とも言われます。 研究開発にかかる経費などが抑えられるため先発医薬品よりお薬の価格を安く設定できます。 |
![]() ジェネリック医薬品のメリットは?
ジェネリック医薬品のメリットは?
![]() 患者様のお薬の負担を軽減します。
患者様のお薬の負担を軽減します。
先発医薬品を後発医薬品に変更することでお薬の負担金を減らすことができます。これは先発医薬品よりお薬の価格を安く設定されているためですが、お薬により価格が異なるため軽減できる金額は異なって来ます。 |
![]() ジェネリック医薬品の効き目や安全性は大丈夫?
ジェネリック医薬品の効き目や安全性は大丈夫?
![]() さまざまな試験を行い、効き目や安全性は確認されています。
さまざまな試験を行い、効き目や安全性は確認されています。
ジェネリック医薬品は、厚生労働大臣による承認を受けなければ、製造販売することができません。厚生労働大臣の承認を受けるためには、開発段階で厚生労働省の定めたさまざまな試験を行い、効き目や安全性が先発医薬品と同等であることが証明されなければなりません。また医薬品は薬事法の基準にも基づいて製造されなければいけないためジェネリック医薬品も先発医薬品と同様に安心してご使用いただけます。
Read More